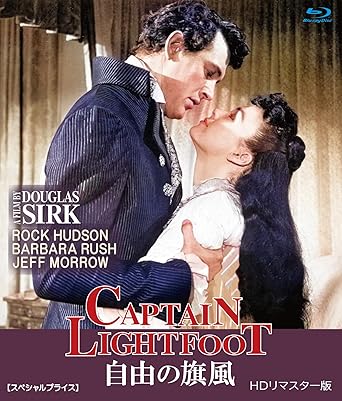アンドレイ・ウジカ『ニコラエ・チャウシェスクの自伝』
(Autobiografia lui Nicolae Ceausescu, 2010) ★★★
「民衆とは、まず画面の切り取り方なのだ。カメラが切り取る長方形の画面がある、そしてこの画面のなかに、沢山の人々がいる。それで十分だ。[…]そしてこの表象が完璧であるためには、部外者、学術用語でいうところの、民衆の内部における矛盾も必要なのだ」(ジャック・ランシエール)
奇妙なタイトルだ。なんとなれば、この映画の作者はチャウシェスクではないし、そもそもこの映画が作られたのは、かれが処刑されてしまった後だからである。しかし、この映画の〈作者〉がチャウシェスクではないというのは本当だろうか。ひょっとしたら、この映画を「ニコラエ・チャウシェスクの自伝」と呼ぶことは間違いではないのかもしれない。映画を見ているうちに、ふとそんなことを考え始めてしまう。全くユニークな映画だ。
おそらくヴィデオで撮影されたと思われる荒い画質のカラー映像で映画は始まる。狭い一室の壁際にチャウシェスク夫妻が座らされている。1989年のクリスマスの日、チャウシェスクがルーマニア社会主義共和国の最高権力者の座から失脚し、妻エレナともども公開処刑された日の映像だ。ふたりは憔悴し、落ち着きがなく、不安を隠しているようにも見える。しかし、カメラの後ろの尋問者が問いを投げかけると、チャウシェスクは毅然として、「大国民議会の前でしか質問には答えない」と繰り返すばかりだ。
アンドレイ・ウジカがハルーン・ファロッキと共同で監督した前作『Videograms of a Revolution』(92) が終わったところから、この映画は始まるのだといってもいい(『Videograms of a Revolution』とこの『ニコラエ・チャウシェスクの自伝』、そしてその次に撮られた『Out of Present』(95) は、ルーマニア社会主義共和国の最後を描いたドキュメンタリー三部作をなす)。しかし、この短いプロローグが終わると、画面は突然、画質の荒いカラーのヴィデオ映像から、モノクロのフィルム映像へと切り替わる。群衆が列をなしてどこかへと向かっている。どうやら国を挙げての葬儀が行われているところらしい。現代史に詳しくなければ、これが1965年に行われたゲオルゲ・デジ(チャウシェスクの前任者であったルーマニア労働者党の書記長)の国葬の映像であることはわからないだろう。
これ以後も、この映画には説明的な字幕やナレーションは一切使われていない。場面は、ド・ゴールのルーマニア訪問(68年)、ソ連のチェコ侵攻を公然と非難するチャウシェスク(これで西側諸国における彼の人気が高まった)、ニクソンのルーマニア来訪(69年)、中華人民共和国を訪問し、熱烈な歓迎を受けるチャウシェスク、イメルダ・マルコスの歌を聞くチャウシェスク夫妻(75年)、アメリカでのカーター大統領との会談(78年)、渡英してエリザベス女王に謁見した際の映像、というぐあいに、なんの説明もなく移り変わってゆく。観客はそのつど、画面のなかの情報と歴史の知識を総動員して、そこに映し出されている出来事が何なのかを理解することを余儀なくされる。その意味では、これはとても不親切な映画であるといってもいい。もっとも、この映画が何かを教えてくれるとするならば、それはグーグルで調べればすぐにわかるような歴史的な知識ではなく、もっと別の何かである。
冒頭のヴィデオ映像をのぞくと、この映画に使われている映像はすべてルーマニア政府の施設に保存されていたものだという。なかには、家族で見るために撮影されたプライベートな映像も混じっているが、いずれにしても、それらはすべてチャウシェスクが望んで撮影された映像ばかりであることにかわりはない。その意味では、これらの映像の作者はチャウシェスクであり、この映画はチャウシェスクの自伝なのだ*1。
だが、その一方で、これらはルーマニアのオフィシャルな映像でもあり、またプロパガンダ映像でもある。ここにはルーマニアの経済政策の失敗も、人民を弾圧する秘密警察も、数え切れないほどの孤児を生み出した避妊禁止令も描かれていない。ここに見えるのは、チャウシェスクが世界に見せたいと思ったものだけだ。ルーマニアの実情を少しでも知っているものならば、ここに映っている栄光と繁栄の陰で実際にはどのような事態が進行していたのかを考えるとき、暗澹たる気持ちになるに違いない。しかし、それ以上に恐ろしいのは、チャウシェスクには世界は本当にこのように見えていたのかもしれないということだ。
ウジカは、一見、このオフィシャルな映像に何の注釈も与えていないように見える。これは、独裁政権を描いた映画としては、例えば、パトリシオ・グスマンの『チリの闘い』や、この映画と同時期に撮られた『光のノスタルジア』などと比べると、まったく異なるアプローチである。しかし、この一見無批判的な態度は見かけだけのことに過ぎない。膨大な映像の中からなにを取捨選択するかという段階からすでに批判の眼差しははじまっている。そしてそれらの映像断片をいかにしてモンタージュ(編集という意味ではなく、異なる2つを並べるという意味のモンタージュ)するかにおいて、ウジカの批判的眼差しは、さりげなく、だがはっきりと示される。だが、何よりも注目すべきは、この作品でウジカが映像にサウンドを加えるやり方だ。
普通の観客はほとんど気づかないかもしれないが、実は、この映画に使われている映像の9割近くは、もともとは音のないサイレント映像だったのである。ウジカはそのほぼすべてに後から音をミキシングして、トーキー映画に再構築したのだ。冒頭のゲオルゲ・デジの国葬のシーンで聞こえる参列者の足音からしておそらく後から付け加えたものだろう。ダンスのシーンで聞こえる曲 "“I Fought the Law and the Law Won”も、ウジカが皮肉たっぷりに付け足したものだ。このようにして、この映画のなかで聞こえる音は、チャウシェスクの演説スピーチなどの例外を除くと、ほぼすべて後から加えられた偽物の音なのである(アーカイヴ・フッテージに後からサウンドを加えて現実を再構築する手法は、セルゲイ・ロズニツァなどによってすでに試みられているが、一人の独裁者の生涯をほぼこの手法だけで描いた映画はむろん、前代未聞だろう)。
こうなってくると、この映画をドキュメンタリーと呼ぶことがはたして正しいのかどうかも、怪しくなってしまう。すべては演出されているのだ。しかし、考えてみれば、もともとのアーカイヴ・フッテージ自体が、チャウシェスクによって壮大に演出されたものだったのである。そして、そのハリウッド・ミュージカルめいた派手な個人崇拝の演出は、他の似たような独裁国家を模倣したものであり、また、そうした国へと伝染して行くものでもあったようだ。中国や北朝鮮を訪問した際のあっけにとられるほどの盛大な歓迎振りは、むろん、チャウシェスク本人が演出したものではないとはいえ、こういした個人崇拝の演出がある種の国家におけるプロトコルになっていたことを物語っている。
このようにもともと演出されていた映像を現実へと近づかせるために、ウジカはそこにほんの少し手を加えただけに過ぎない。ウジカの演出は、うっかりすると見逃してしまう、いや、聞き逃してしまうかもしれないほど、さりげないものである。だが、注意深く見、耳を澄ましているならば、そこに不穏な何かが見え隠れしていることに気づくはずだ。
最初、映画はクロノロジーに従って進んでいくのだが、映画がなかば近くに達し、78年にチャウシェスクがイギリスを訪問してエリザベス女王に謁見するあたりまで描くと、ウジカはとつぜん映画の時間を巻き戻す。それはあたかも、歴史の映像をたどり直し、そこに見えないひずみを探そうとするしぐさのようにも思える。最初に映し出されるのは、75年の大洪水の映像だ。すでに不穏な空気はあたりに漂い始めている。ついで、77年の国会でチャウシェスクが演説している映像が映るのだが、演説の途中で不意に画面が真っ黒になったかと思うと、地響きのような音が響き渡り、形容しがたい叫びのようなものが聞こえてくる。この後に続く場面で明らかになるのだが、実は、これは、この国会のさなかに実際にルーマニアを見舞った大地震の音なのだ。数十秒間続いたその地震の音は、マイクロフォンによって約半分ほど録音されて残っていた。ウジカはそのサウンドを使って、この場面を再構築したのである。だが、そんなことを知らないわれわれがこの場面を見るとき、そこに聞こえてくるのは、チャウシェスクが演出した栄光と繁栄のルーマニアの背後で、ルーマニアの現実がきしみ、叫び声を上げる音であるとしか思えない。
この映画を表面的に見る限りでは、チャウシェスクは最悪の独裁者には見えない。歴史に残る悪女といわれるチャウシェスク夫人も、上品なご夫人のように思える(こころなしか、すこしダニエル・ユイレに似ている)。この映画のなかには一人として彼らに異を唱えるものは映っていない。唯一、党の集会でチャウシェスク再選に異を唱えた党員の声(この映画でただひとつ画面に見える形で現れる不協和音)も、会場を埋め尽くしたチャウシェスクの支持者たちの拍手と歓声によってかき消されてしまう。
ひょっとすると、チャウシェスクはマルクス=レーニン主義によってルーマニアが理想の国家として繁栄することを本気で信じていたのかもしれない。しかし、悲劇的なことに、かれには自分の信じるイデオロギーと現実との落差がまるで見えていなかったのである。『Videograms of a Revolution』とこの映画を続けてみれば、そのことがよりはっきりとわかるだろう。
映画は、最後に、冒頭のヴィデオ映像にふたたび戻ってくる。あたかも、このプロローグとエピローグに囲まれた部分は、チャウシェスクの最後の回想であったのようだ(ベルトルッチの『ラスト・エンペラー』を少し思い出させもする構成である)。ざらざらとした画質の荒さが、われわれをふいに生(なま)の現実へと引き戻す。デモ隊に発砲命令を出したのはお前なのかと問い詰める尋問者に、何のことかわからないと答えるチャウシェスク。ここにいたっても、彼には何も見えていない。この後になにが起きたかはだれもが知っているだろう。映画もあえてそれは描かない。
プロパガンダ映像を用いてプロパガンダ映像を批判する、歴史を描きつつ歴史の虚妄を暴く。この映画でウジカがやろうとしているのは、そんな綱渡りのような試みである。現代史に無知なものにとっては、ちょっととっつきにくい映画かもしれない。しかし、独裁国家が遠い昔の話でないことは、われわれもつい最近思い知らされたばかりだ(むろん、北朝鮮のことを言っているのだが)。そういう意味でも、これは今だれもが見るべき映画のひとつだと思う。
ウジカは、コルネリウ・ポルンボイウとクリスティ・プイウらに代表されるルーマニアの若い世代の映画監督たちを高く評価し、エールを送っている。フィクションとドキュメンタリーという逆の方向からだが、目指しているものは同じだと。ポルンボイウとプイウについては、5年ほど前にここで簡単に紹介した。ウジカの作品と合わせて、こちらも見ていただきたい。