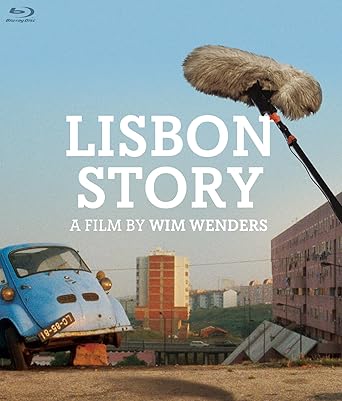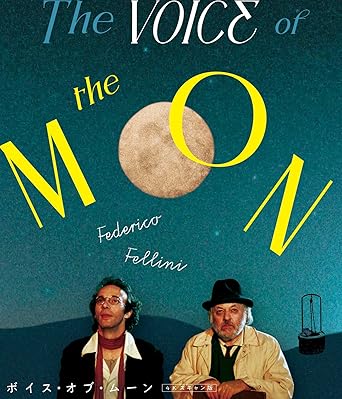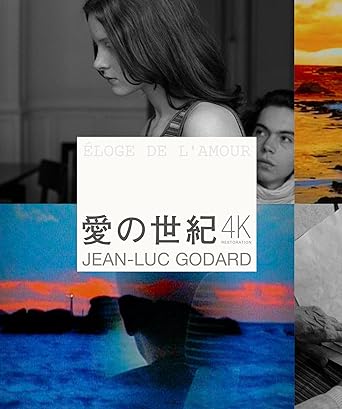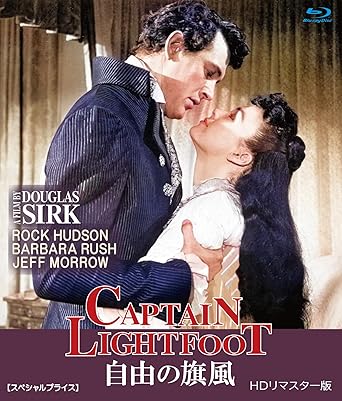わたしが見ることができたハンス・シュタインホフの映画は結局3本だけだが、この監督には確かな演出力があることが確認できた。彼が映画を撮ったのがたまたま(本当にたまたまなのか?)ナチス・ドイツでなかったならば、ひょっとしたら今頃は巨匠として名を残していたかもしれない。
ハンス・シュタインホフ『老いた王と若き王』(Der alte und der junge König - Friedrichs des Grossen Jugend, 1935) ★★
18世紀プロシア におけるフリードリヒ・ヴィルヘルム1世と、その息子の王子フリードリヒ2世との確執を描いた伝記映画。軍人気質の権威主義的な父フリードリヒ1世とは対照的に、フリードリヒ2世は、フルートを嗜んだりする芸術家気質の人物だった。父フリードリヒ1世は、国事にもあまり関心のないひ弱な息子を事あるごとに叱責し、なんとか立派な世継ぎにしようとするが、息子はかえって反発する。このままでは父親の支配から逃れられないと考えたフリードリヒ2世は、とうとうフランスへの亡命を試みるが、直前で計画は露見し、父親によって投獄されてしまう。フリードリヒ1世は最初、息子を処刑することも考えるが思い直す。しかし、彼が下した処罰はそれ以上に残酷なものだった。フリードリヒ1世は、息子の親友で、かれの亡命を手伝ったカッツェを、息子の目の前で処刑したのである。この事件を境に、フリードリヒ2世は父親に絶対的服従を誓い、人が変わったように祖国プロシアのために献身的に働くようになるのだった。
息子フリードリヒ2世が、臨終の父親に、「お父さんは間違っていなかった」と語りかけ、フリードリヒ1世が「この国を偉大にするのだと言い残して息を引き取る場面がこの映画のクライマックスである。オフュルスの『マイエルリンクからサラエヴォへ』を少し思い出させる話ではあるが、ここには恋愛要素はまったくと言っていいほどない(シュタインホフの映画を見たのはまだ3本だけだが、恋愛要素がほとんど皆無であるのはただの偶然だろうか)。
フリードリヒ2世(フリードリヒ大王)を描いた映画はサイレントの時代からドイツで撮られていた(『Fridericus Rex』(1922))。しかしナチスの時代になってそれが量産され始める背景には、この英雄的指導者とヒューラ―を重ね合わせようとする意図があったことは間違いないだろう。またエイゼンシュテインを持ち出すならば、『ヒトラー青年』が『戦艦ポチョムキン』を意識していたのに対して、この作品は『イワン雷帝』に当たる作品だということもできる(もっとも、『イワン雷帝』が撮られるのはこの映画の約10年後であるが)。
この映画はたしかに、『ヒトラー青年』のようなあからさまなプロパガンダ映画ではない。しかし、諸外国、とりわけフランスが祖国プロシア(ドイツ)と比べて侮蔑的に言及されていたり(フリードリヒ2世は留学 をきっかけにフランスにかぶれて音楽にうつつを抜かすようになる)、何よりも、権力者の命令には絶対的に服従すべきであるというメッセージが、いささかグロテスクな物語を通して語られるという部分に、プロパガンダ的な要素が多分に含まれていると言っていいだろう。
父フリードリヒ1世を演じているのは『嘆きの天使』のエミール・ヤニングス。いつものようにいささかオーバーアクト気味ではあるが、存在感は圧倒的であると言うしかない。ナチが政権を握ったあともドイツに残って映画に出続けたヤニングスは、戦後、映画界から追放されることになるだろう。ちなみに、『嘆きの天使』は退廃的であるとして、ナチが権力を掌握した33年に公開禁止になっている。
脚本を書いているのが、ラングが亡命したあともナチス・ドイツに残り続けたテア・フォン・ハルボウであるというのも、見逃せないポイントである。
ハンス・シュタインホフがどのような人物であったか、どのような政治信条を持っていたか、ナチとの関係はいかなるものであったかなどについて、わたしはあえて調べずにこれを書いている。わたしがそうだったように、事情を何も知らないものが見たならばたぶん、この作品にも『ヒトラー青年』と同じような曖昧さを感じるのではないだろうか。テア・フォン・ハルボウを始めとして、この映画に関わった作者たちは、おそらく、先程書いたようなプロパガンダ的な目的でこの作品を作っていたに違いない。しかし、自分のせいで親友が処刑されたのをきっかけに、まるで意思をなくしたロボットのように父親の望むとおりに振る舞うフリードリヒ2世を見ていると、命令には絶対的に服従すべしという表面的なメッセージの裏側に、それとは真逆なメッセージが込められているのではないかとつい思えてしまうのである。しかし、これはたぶん深読みに過ぎないのだろう。
1935年といえば、レニ・リーフェンシュタールの『意志の勝利』が公開された年である。しかし実は、この年に撮られたナチのプロパガンダ映画の数は、その前後の時期と比べると、少なかったという。
『クリューガーおじさん』(Ohm Krüger, 1941) ★★★
19世紀末から20世紀初頭にかけて南アフリカのトランスバール共和国と、この地の金鉱の独占を狙うイギリスとの間で行われた帝国主義戦争、いわゆるボーア戦争を、トランスバール大統領クリューガーの視点から描いた映画。オランダ系アフリカ人であるボーア人たちとイギリスとの戦争という、『老いた王と若き王』以上に当時のドイツとはまったく関わりのない話であるが、この作品のほうがプロパガンダ色はより強い。
イギリスの支配から祖国を守ろうとするボーア人たちと大統領クリューガーの姿は、「自由と大地」のために戦っていたドイツ人とヒトラーに容易に重ねられるだろう。後半、イギリスとの戦争が激しさを増してゆくなかで、イギリス人たちは文字通り鬼畜のような描かれ方をされていく。わたしが今、プロパガンダ映画だとわかって見ていても、イギリス人たちに対する憎悪が自然と湧き上がってくるくらいだから、当時のドイツの観客たちはこの映画を見てさぞや好戦的な気持ちにさせられたことだろう。
しかし、この映画もやはりプロパガンダ映画としてはどうにもモヤモヤとした気分にさせる作品である。イギリス人たちは、戦争とは関係のない民家を焼き払い、民間人を逮捕して収容所に入れるのだが、その収容所で、満足な食事も与えないし、チフスが蔓延しても何の手も打とうとせず、異を唱えるものがあれば撃ち殺すという冷酷なイギリス人たちの姿は、第二次大戦を描いた映画におけるナチスの紋切り型のイメージとそっくりなのである。はたして、このアイロニカルなシーンをどのように理解すればいいのだろうか。
クリューガー大統領を演じているのは、またしてもエミール・ヤニングス。『老いた王と若き王』に比べるとずいぶん抑えた演技をしているが、そもそもメーキャップがすごくて元の顔はほとんど見分けがつかない。クリューガーの息子はイギリスに住んでいて、イギリスびいきの平和主義者になっているのだが、この息子と父クリューガーとの関係は、『老いた王と若き王』における父ヤニングスと息子の王子の関係を、ある意味で繰り返していると言っていいだろう(クリューガーは不甲斐ない息子を一度は勘当する。息子は、イギリス人の本性を目の当たりにして祖国のために戦うようになり、戦場でようやく父と再会するが、その頃には父ヤニングスは視力を失い息子の顔をほとんど見ることが出来ない)。
この映画にも、ゲッベルスのお気に入りだったという『戦艦ポチョムキン』を思い出させるシーンが少なからずある。収容所で食事に出された腐った缶詰を突きつけて抗議した女が殺される場面は、『戦艦ポチョムキン』の腐った肉のエピソードを思い起こさせる。その収容所に入れられている妻と子供に会いに来たクリューガーの息子は捕まり、小高い丘に立つ一本の木で絞首刑に処せられる。かれの妻を先頭に、女たちが抗議のシュプレヒコールを上げると、イギリス兵たちは彼女らを容赦なく撃ち殺してゆく。彼女たちが丘を転げ落ちるように撃ち倒されてゆくシーンは、オデッサの階段を意識したものに違いない。
ところで、レニ・リーフェンシュタールは『低地』(Tiefland) を製作中にゲッベルスから撮影を妨害されたという。「国民の戦争への協力 (war effort) のために、自作のセットを解体してスタジオを『クリューガーおじさん』と『老いた王と若き王』の撮影のために明け渡さなければならなかった」と彼女は語っている。しかし、時期から言って、『老いた王と若き王』の方はたぶんリーフェンシュタールの勘違いで、『Der grosse König』の間違いであろう。リーフェンシュタールは自分のナチへの関与を否定する発言を繰り返していた。この発言もそういう文脈で理解しなければならないのであろうが、いずれにせよ、この時期には、彼女のかつての栄光には陰りがあったことは確かであろう。