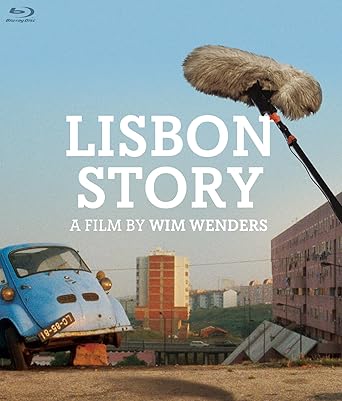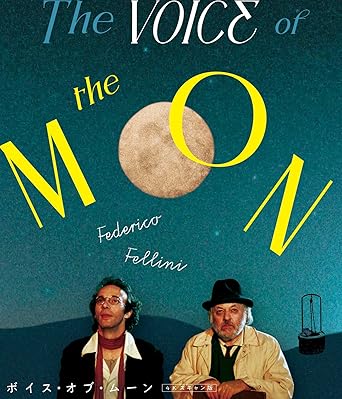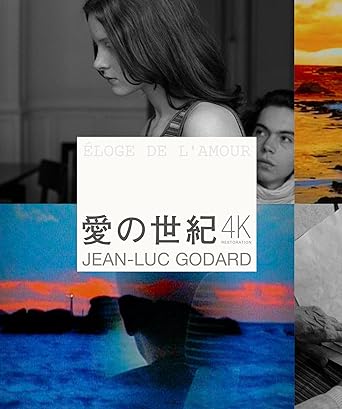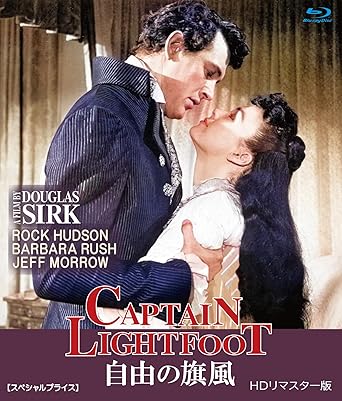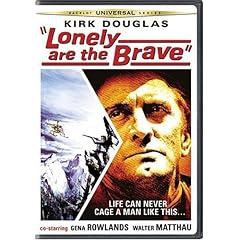デイヴィッド・ミラー『脱獄』Lonely are the Brave (62)
デイヴィッド・ミラーという監督は、日本では『ダラスの熱い日』が多少とも知られているだけで、さして評価が高いわけではない。アメリカ本国でも、オリジナリティーに欠ける凡庸な監督というのが、一般の評価である。そして、多分、この評価は間違ってはいない。実際、この監督には、作家として称揚すべき個性も野心も欠けているのだ。しかし、わたしは彼が撮ったこの『脱獄』という映画が大好きなのである。
出来がいいか悪いかといえば、取り立てて出来のいい作品ではない。しかし何とも忘れがたい作品だ。
冒頭、見渡す限りの荒野をカウボーイ姿のカーク・ダグラスが馬に乗って登場する。だれが見ても西部劇だ。しかし、彼が馬で大きな河を渡ると、その先には、アスファルトの道路を車が激しく往来している。まるでヴェンダースの映画のような始まり方だ。
カウボーイ男は、クラクションを浴びせかけられるのもものともせず、馬に乗ったまま道路を横断する。近くの一軒家で、女がひとり家事をしている。ジーナ・ローランズだ。表から聞こえてくる蹄の音になにかを察して、女は笑みを浮かべる。ほどなくして戸口に現れるのは、無論、カーク・ダグラスだ。こんなふうに、この映画は帰郷の場面で始まるのだが、ここは、『ラスティ・メン』の冒頭で、ロデオ乗りのロバート・ミッチャムがふらりと帰ってくる少年時代の思い出の家のような親密な場所ではないし、女も彼の家族ではない。実際、この男には帰るべき場所などどこにもないのだ。それがこの映画のテーマでもある。
ジーナ・ローランズとカーク・ダグラスの交わす会話から、女はダグラスがかつて愛した女性で、今は彼の親友と結婚して子供もいること、そしてその親友は町の牢屋に入れられていることがわかる。いまだにあてどない生活をしているのかと女に聞かれたダグラスは、こう答える。「おれはフェンスが嫌いなんだ」。このセリフを聞いてはたと気づく。この映画はキング・ヴィダーの西部劇『星のない男』の続編なのだ。あの映画を見たものなら、土地を囲い込む有刺鉄線を異常なほど憎む主人公のカウボーイのことを忘れることはできないだろう。その主人公を演じていたのも、カーク・ダグラスだった。
『脱獄』の脚本を書いたダルトン・トランボがこのことをどれほど意識していたかはわからない。しかし、この映画を自らプロデュースしているカーク・ダグラスは、間違いなくこの2つの作品の血縁関係を意識していたと思う。『星のない男』の続編といったが、むろん、本当の続編ではない。『星のない男』とその7年後に撮られた『脱獄』では、主人公の名前は違うし、物語の時代設定は10年どころか、100年近い隔たりがある。『星のない男』で、自分の行動を制限するフェンスを嫌悪し、それが原因でときに理解しがたい暴力の発作に襲われもした主人公のカウボーイは、『脱獄』でも相変わらず、牢屋の鉄格子はもちろん、フェンスや国境といった境界線に対して嫌悪感を示す。しかし、『脱獄』のダグラスは、ひとつの場所に安住できない自分の性癖がすでに時代遅れなものだとわかっており、なかば仕方なくその性癖に従っているようにも見える。
親友であるジーナ・ローランズの夫が牢屋に入れられていることを知ったカーク・ダグラスは、牢屋に入れてもらうため、酒場でわざと騒ぎを起こす(この酒場の場面では、客の一人の戦争で片手を亡くしたという男が、陰険に描かれているところが面白い)。『星のない男』では内側の暴力を抑えきれない男を演じていたダグラスだが、『脱獄』ではもっぱらいわれなき暴力を受けるだけの存在になっている。牢屋でサディスティックな保安官ジョージ・ケネディにリンチされるシーンがその典型だ。
『星のない男』の主人公を現代社会にさまよわせるという主題は、野心的であり、美しい。しかし、監督の手腕がそれに見合っているかという問題はたしかに残る。似たような冒頭を持つフォードの『捜索者』が、ほとんど視線のやりとりだけで人間関係をすぐにわからせてしまうのにくらべ、『脱獄』のローランズ、ダグラス、マイク・ケインの関係の描き方は、もたもたしているわりに舌足らずだ。牢屋の場面もお世辞にもうまいとはいえない。たぶんこの監督は人間関係を描くのが苦手なのだ。後半の山越えのシーンが感動的なのは、ここではカーク・ダグラスのほとんど一人舞台になるからだろう。このクライマックスで、ダグラスは小高い岩山を馬に乗ったまま乗り越えようとする。途中で馬を捨てれば楽にいけるものを、愛馬を捨てることができず、越境は次第に困難なものとなってゆく。この主題がまた、船で山を登るヴィダーの西部劇『北西への道』に似てしまっているのは、はたして偶然なのか。
巨大な山にひとりで挑み、ヘリコプターをライフルで撃ち落とそうとするダグラスはまるで、愛馬ロシナンテに跨ったドン・キホーテのようだ。『星のない男』が『ドン・キホーテ』前編だとしたら、この後編では、西部劇はすでに物語のなかにしか存在しない世界になっており、主人公もなかば自意識に目覚めている。その主人公を追いつめる保安官たちが、ジョージ・ケネディ、ウォルター・マッソーといった、主に60年代以後に活躍し始める新世代の俳優たちであるというのも、実に象徴的だ。
ネットでざっと調べてみて、日本でもこの映画が好きな人間が意外と多いことがわかった。しかし、この作品と『星のない男』との血縁関係をだれも指摘していないようなのには驚く。見ていればだれもが気づくはずだ。それに気づかないということは、『星のない男』さえ、だれもまともに見ていないということなのか。
最後にやってくるあっけない結末は、アメリカン・ニューシネマを思わせるというコメントも散見された。たしかに、『バニシング・ポイント』に代表されるような、無軌道な暴走の果ての自死に、それは似ていなくもない。しかし、この映画を映画史のなかに正当に位置づけたいのなら、『星のない男』を見てからにしてほしい、とだけいっておく。