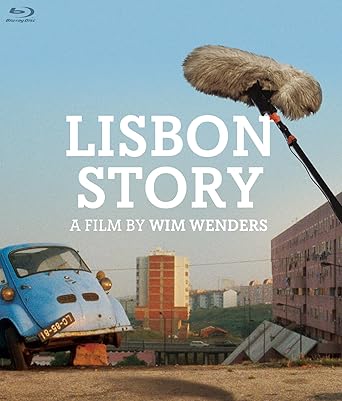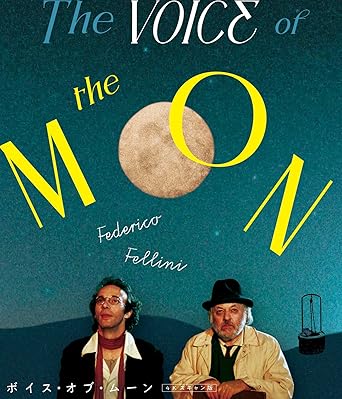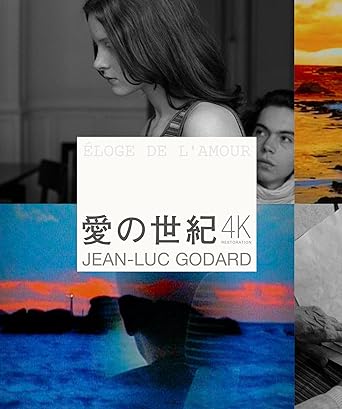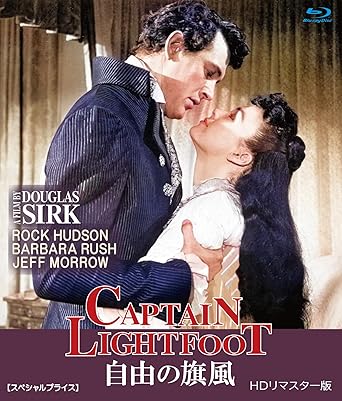フセヴォロド・プドフキン『脳の機能』(Mekhanika golovnogo mozga, 1926) ★
脳神経が動物の行動に及ぼす働きを描いた純然たる科学映画。カエルから始まって、犬、猿というふうに動物生体実験の様子が描かれてゆき、そこから得られた結論から、最後に、人間における脳の機能が考察される(さすがに人間の生体実験までは描かれない)。
パブロフのレニングラード研究所を取材したこの科学映画をプドフキンが撮るに至った詳しい経緯はわからないが、かれが若い頃に化学(化け学の方)を学んでいたことも少なからず関係しているのだろう。パブロフがこの映画にどのように関わったかについても詳細はわからない。完成した作品に対するパブロフの反応も曖昧で、気に入っていたという話もあれば、不満を漏らしていたという話もある。
それにしても、知らずに見たら、まさかこれがプドフキンの映画だとは誰も思わないだろう。
ちなみに、ヴェルトフも若い頃に脳心理学を学んでいたし、ドヴジェンコも『ミチューリン』という科学者映画を撮っている。ソ連における科学と映画の関係は意外と奥が深い。
フセヴォロド・プドフキン『A Simple Case』(Prostoy sluchay, 1932) ★★½
プドフキンがこの映画の制作に取り掛かったのは1928年のことだった。かれは最初この映画をトーキーとして制作しようとしたが、結局、サイレントとして作ることを余儀なくされた。最初、「人生は美しい」のタイトルで公開されたものの、批評家からは攻撃され、大衆からは「よくわからない」と言われたため、プドフキンはこの映画を編集し直して「A Simple Case」というタイトルで32年に公開し直すことになる。プドフキンにとって非常に不幸な作品だった。
1928年3月のソヴィエト映画会議において、映画作品は社会的・政治的な内容についての正確な基準を含んでいて、「万人に理解できるものである」べきであるという声明が発表される。映画の評価基準を定めた党によるこの正式な見解は、ソヴィエトの映画作家たちに直接的・間接的に大きな影響を与えることになるであろう。1935年の全ソ連邦映画人会議において社会主義リアリズムの理論が導入されるよりもはるか前のこのときから、ソヴィエトの映画作家たちは周りの空気が変わり始めていたことを感じていたに違いない。
それと同時に、1928年は、ソヴィエトの映画作家たちがトーキー映画を視野に入れて映画を作り始める時期でもあった。ソヴィエトにおける最初のトーキー映画が公開されるのは、31年製作の『女一人』になるのであるが、ヴェルトフの『カメラを持った男』(29) やプドフキンのこの『A Simple Case』など、この時期に制作された映画には、当初はトーキー映画として考えられていた作品が少なくない。
この映画が失敗したのは、むろん、こうした外的な理由だけではないだろうが、こうした状況がこの映画の命運に少なからぬ影響を与えたことは確かだろう。
単純な物語のわりには、正直、わかりにくい映画だが、ときおり現れる映画的瞬間にはハッとさせられる。大地にひとり立ち尽くす男。空を流れる雲。一本道を走ってくる女のカットイン。曲がりくねった道を捉えたロングショット。男に駆け寄る女。冒頭のこの一連のショットは、あまり意味のないハッタリのようなカットつなぎだと思いながらも、引き込まれるのは確かだ。男が駅で女と別れるシーンのあとに、突然、「3分前」という字幕が挿入され、階段を降りる無数の脚をスローモーションで捉えたショットが続く場面もとても不思議な感覚を与える。
プドフキンの映画のモンタージュは、いわゆる「モンタージュ」よりも、ストーリーを効率的に語るためのハリウッド流「カッティング」に近いと言われたりもする。たしかに、プドフキンが理論的著作のなかで表明していたのはそのような映画だったろうが、当然ながら、プドフキンの実際の映画がかれの理論通りにできているわけではない。そういう意味では、この映画は、当初彼が考えていたものとはずいぶん別のものになってしまったが、プドフキンの作品のなかでもとりわけ実験的な一本とさえ言えるかもしれない。